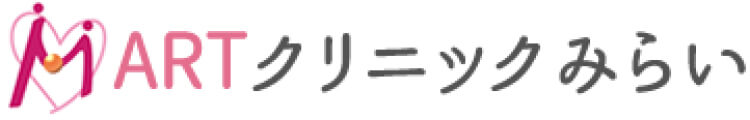先進医療
1. 子宮内膜刺激術(SEET法)
日本産婦人科学会は、多胎を防ぐ観点から、原則1個の胚移植を推奨しています。
SEET法では、一段回目に移植する初期胚の代わりに胚培養液を子宮に注入することで子宮内膜の胚の受け入れ体制を整えた後、二段階目に胚盤胞を移植する方法です。融解胚移植ホルモン補充周期において胚移植の2〜3日前に培養液をカテーテルで子宮内に注入します。
SEET法の最大のメリットは、移植に用いる胚盤胞を1個にすることで、多胎を防ぐと同時に、妊娠率が向上する可能性があります。
2. 子宮内膜着床能検査
子宮内膜には受精卵が着床可能なタイミング(着床の窓)が存在します。
着床の窓が一般的なタイミングからずれていないか、関連する遺伝子の発現レベルを調べて確認します。
ずれがあると判断された場合は、胚移植のタイミングを検査結果に合わせて移動させます。
3. 子宮内フローラ検査
子宮内に存在する細菌の種類と量を測定し、そのバランスを調べます。
近年の遺伝子解析技術の進歩により、子宮内にも微量な菌が存在し、複数の菌による子宮内細菌叢を構成していることが明らかとなってきました。膣内細菌叢と同じく、ラクトバチルス(乳酸菌)優位な環境が生理的であり、この割合が低下すると、妊娠成功率が低下、挙児獲得率が低下するとの報告があります。
4. PICSI
(Physiologic intracytoplasmic sperm injection)
顕微授精(ICSI)に用いる精子は、一般的に運動性と形態によって選別します。
PICSIでは、DNA損傷を起こしていない成熟した精子がヒアルロン酸に結合しやすいという性質を利用して、より良好な精子の選別をします。
5. タイムラプスインキュベーター
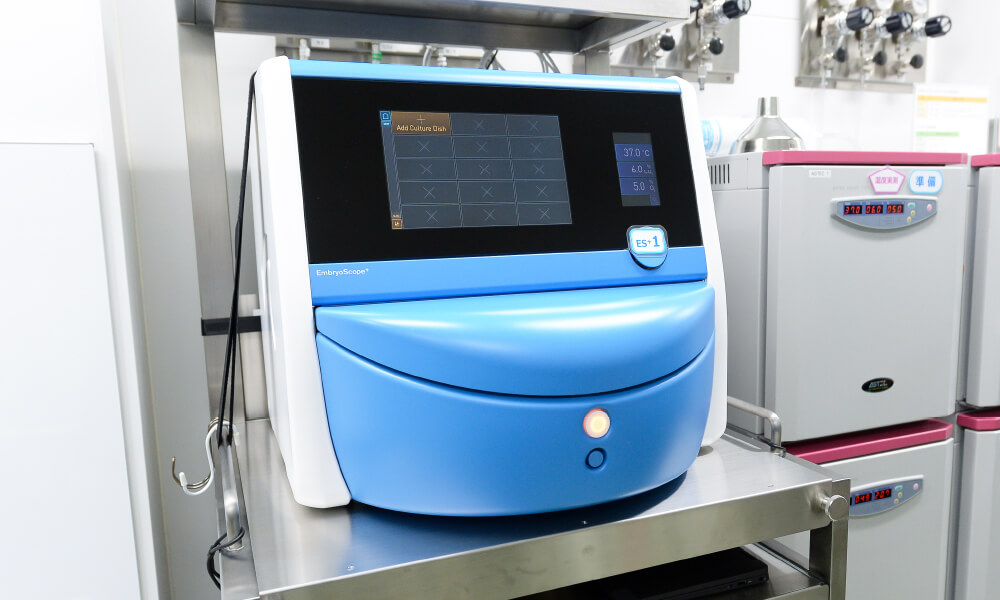
受精卵を培養しながら10分毎に写真撮影し、受精卵の詳細な変化を記録することができます。
特殊治療
1. 卵子活性化
顕微授精を行ってもまったく受精しない原因不明の受精障害があります。
これは、精子が卵子の中に入っても卵子の活性化が起こらず、次のステージへの成長が阻害されていると考えられます。
このような場合、カルシウムイオノフォア処理という特殊な方法で卵子を人為的に活性化させて受精を助けています。
2. 二段階胚移植
分割胚移植と胚盤胞移植を同一周期に続けて行う方法です。1回目の移植により子宮内膜が刺激を受け、2回目の移植胚の着床率が上昇すると報告されています。
反復不成功症例が主な対象となります。
3. 未熟卵体外培養体外受精
未熟卵の段階で採卵し、体外で成熟させた後に体外受精や顕微授精を行う方法です。
排卵誘発剤をほとんど使用せず、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクのない、負担の少ない方法です。
多嚢胞性卵巣の方が主な対象となります。
4. 卵子凍結(未受精卵凍結)
受精卵と比較して卵子の凍結融解後の生存率はやや劣るとされていましたが、技術向上により遜色ないものとなり、当院でも実績を上げています。
卵子凍結を応用する場面としては、採卵当日に予期せず精子が採取できなかった又はみつからなかった場合、精巣手術(無精子症治療)後の極少精子症例において、ワンチャンスの精子融解・顕微授精に備え、より多くの卵子を確保しておきたい場合、ガンを患った未婚女性で治療後の妊孕性低下が心配される場合、将来の妊孕性低下に備えた社会的適応などが挙げられます。
5. 感染性慢性子宮内膜炎検査
慢性子宮内膜炎は、不妊原因の一つです。この疾患は子宮内膜の炎症を引き起こしますが、ほとんどの場合自覚症状がありません。この検査では、慢性子宮内膜炎の原因菌を検出し、適切な抗生物質と治療法を提案します。
6. G-CSF療法
着床時期の内膜にはGM-CSFというサイトカインが多く存在し、着床に大きくかかわっているのではないかと考えられます。
海外からを中心に、G-CSFの投与により、子宮内膜が厚くなった、薄い内膜でも着床した、という報告が増えています。
反復不成功例を対象にご夫婦の同意を得て当院でも試みています。
7. PRP子宮内注入療法
PRP子宮内注入療法は、ご自身の血液から抽出した高濃度の血小板血漿(PRP)を利用した治療です。
PRPには、細胞の成長を促す物質や免疫に関わる物質が多く含まれ、組織の修復・治癒・血管新生を促すことが知られています。
近年注目の『再生医療』の一種で、整形外科領域(スポーツ選手の損傷修復)や歯科・皮膚科領域などで目覚ましい効果が報告されています。産婦人科領域においては、子宮内に注入することで、子宮内膜の環境改善、胚の着床・成長が促進されることが期待されています。子宮内膜が薄い方、良好胚を移植してもなかなか着床しない方、などが対象となります。
*当院は、再生医療を実施するための厚生労働省からの認定を受けています。
8. PFC-FD療法
ご自身の血液から抽出した高濃度の血小板血漿を子宮内又は卵巣内に注入する方法です。
子宮内に注入することで、子宮内膜の環境が改善され、受精卵の着床、成長が促進され、卵巣内に注入することで、発育卵胞の増加を期待しています。(血小板血漿とは、血液を遠心分離器にかけて成分を分離し、おもに血小板を取り出したものです)
9. 着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)
妊娠不成功・流産の最も大きな原因は、胚の染色体異数性(染色体数の過不足)であり、着床前に染色体の数を調べ、異数性胚を除いて移植を行うことで、妊娠率の向上、流産率の低下、治療期間の短縮が期待されます。
PGT-Aは、海外においてはすでに臨床応用されていますが、現在日本においては、日本産科婦人科学会による臨床研究として、条件を満たした方に対し、選任施設においてのみ可能です。ご関心のある方は診察時に医師にお尋ねください。